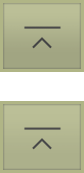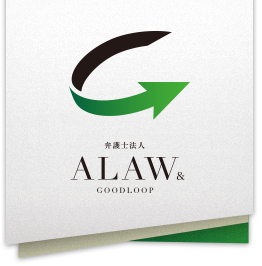物価対策、一時金支給か消費税減税いずれが是か?が選挙での大きな争点。これは、皆様ご存じのとおり。物価上昇率が3%とか、2,7%とか言われるが、とりわけ食料品価格上昇率は、私個人の肌感覚では8%を超えるように感じた、だから国民全体の重大問題、選挙の争点とされたのは当然。
これに対して、最近の7月31日の植田日銀総裁の会見要旨を読むと、いろいろと考えさせられる点がいっぱい出てくる。
「問い ・・・基調的な物価上昇率の現状は?」
「答え ・・・ごくゆっくり上昇が続いているが、まだ2%には届いていない」
ここでびっくり、あの8%も超えそうな食料品価格上昇は、どこにいったの?
そこで、「基調的な物価上昇率」という言葉(植田総裁がよく使用されるとのこと)をインターネットで調べてみた。
「基調的な物価上昇率」とは、様々な一時的要因の影響を取り除いた、基調的なインフレ率(いわゆる「コア指標」)のこと
確かに、同じ消費者物価とはいっても、季節変動や天候などの一時的要因に左右される生鮮食料品価格が取り除かれるのはわかる。
「まだ2%には届いていない」などと植田総裁が涼しい顔でおっしゃるのは、現在の物価高、食料品価格上昇は、コストプッシュ・インフレーションであって、日銀の責任領域外だからとのお考えなのだろうか?
会見要旨中、需要サイドからの物価上昇は、金利を上げて景気過熱を冷やして物価を下げる、供給サイドの要因では、利上げで、景気を冷やして所得を減らす、本当に望ましいのかどうかは難しい点だと言われている。
確かに、金融政策は、需要を抑える効果は大きいが、供給を増加させる効果は弱い。そのためコストプッシュ・インフレーションは、供給サイドの要因のものであって、金融政策に出番はないとお考えなのだろうか?
しかしながら、現在の食料品価格の高騰が、まったく日銀と無関係なのだろうか? 2023年、2024年中、世界の先進国中、日本を除く、欧米各国でインフレが猛威を振るい、一方我が日本だけはデフレで超低金利政策を続けていたのが、現在気がついてみれば、日本は先進国中一番物価が上昇していて、遅まきの利上げをようやく始めたところである。
他の先進国で特段食料品価格上昇が見られないのに日本だけがなにゆえ食料品価格高騰に悩まされているのか、その原因は何か?
日銀が利上げを始めたとはいえ、政策金利0.5%からインフレ率3%を差し引けば、マイナス2.5%、他の先進国が高金利であるのに対し、日本は、実質マイナス金利では、円安他国通貨高となるのは避けられない。
円安とは、日本の通貨円の物を買う力が弱いことになり、輸入物価高につながり、食料自給率4割で食料品を輸入に頼る国日本の国内の食料品価格が高騰するのもやむを得ない。
そうすると、日本の食料品価格高騰は、基調的な物価上昇率とは無関係であり、日銀の責任領域ではないと植田総裁が涼しい顔で言われたとしたら、納得できない。
会見の最後のほうで、「問い 為替は物価にどう影響するか。」との質問に対し、植田総裁は、「答え 為替が物価見通しにただちに影響するとはみていない。見通しの前提としている為替の水準から足元の水準がずれているわけではない」と答えておられる。私には、これは円安を容認したものに聞こえた。
私は、2022年夏ころのブログで「黒田総裁発言、ネットで大炎上」関連で書いたブログの中で「(食料品高騰の消費者への影響を)買い物は奥様任せで、休日でもスーパーに行かれない総裁にはおわかりいただけないかもしれないが・・・」
「(黒田総裁の)無制限指し値オペ毎日実施によって市場に過剰流動性を供給し続けるのは・・・正気の沙汰ではない」と書いた。
これは、日銀の金融政策による通貨円過剰供給が円安に、円安が輸入物価上昇につながることを恐れて述べたものである。
誤解のないように、私は、日銀が利上げを全くしないなど言っているわけでも、日銀の慎重な利上げを非難しているわけでもない。
私個人は、黒田総裁の量的質的金融緩和は大いに評価している。それが限界に突き当たった後のイールドカーブなんたらやらマイナス金利政策には反対であり、それらを一挙に止めてしまった現在の植田総裁も大いに評価している。
しかしながら、為替と物価上昇は無関係とばかり、円安は日銀我関せずの円安に危機意識のないノウ天気な発言で市場を円安にしてしまうことは避けていただきたい。
上記の円安容認ともとれる発言により市場では円安が進んだとそうである。同発言は今回の会見中、失言中の失言といっても過言ではない。
なるほど中小企業経営者から見れば、金利を上げるのはゆっくりでお願いしたい。
それでも、現在の実質マイナス金利を続けるわけにはいかない、ゆっくり慎重でもとにかく金利正常化、金融正常化をあくまでも続けていくことについて市場から信頼される姿勢を維持していただきたい。
本コラムや事件相談は、093-967-1652の弁護士永留に連絡して下さい。 以 上